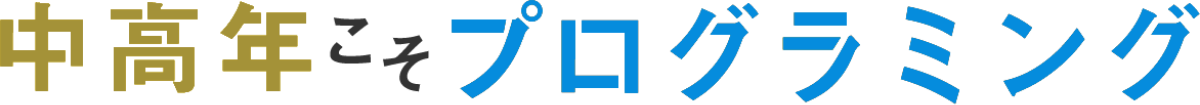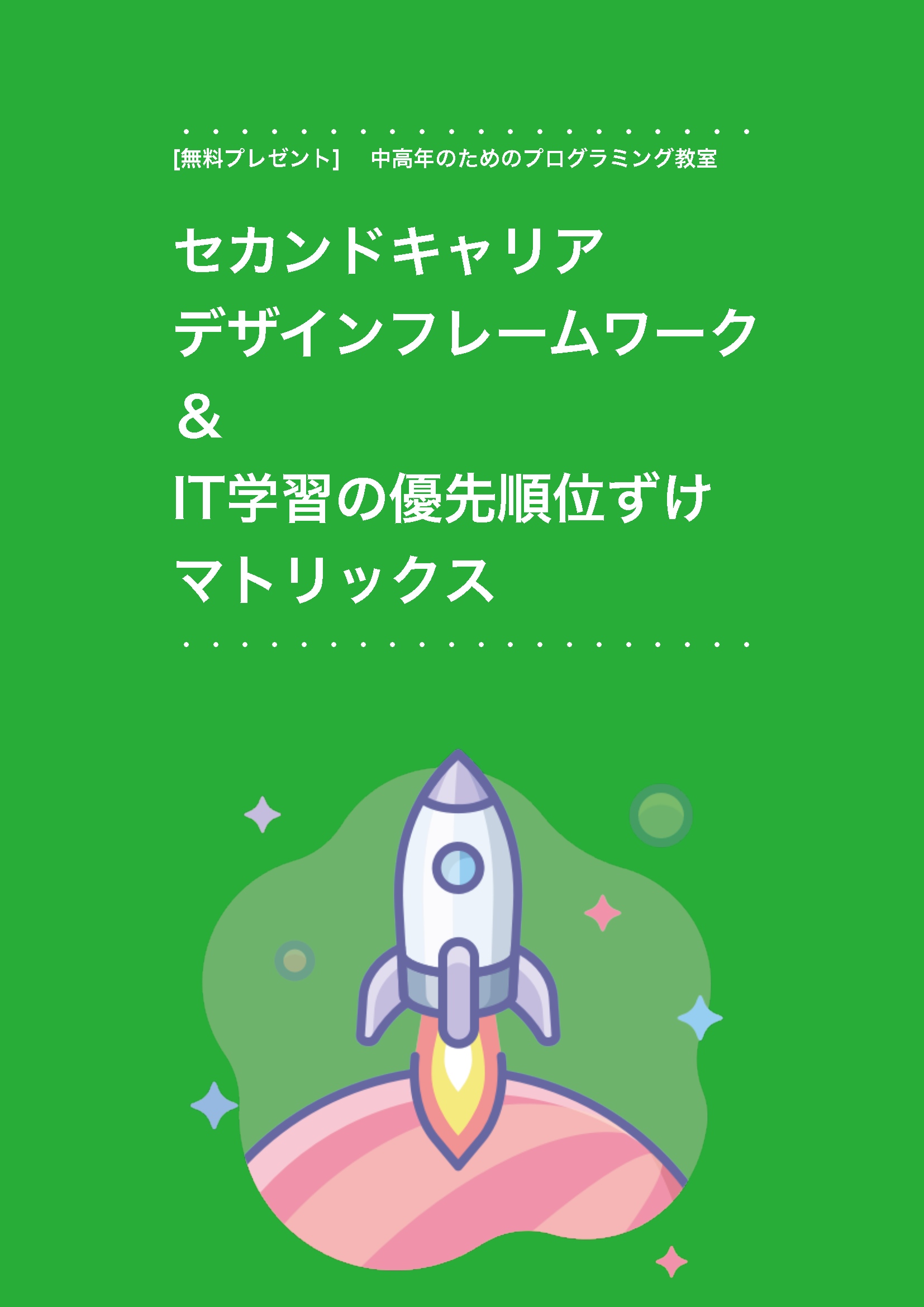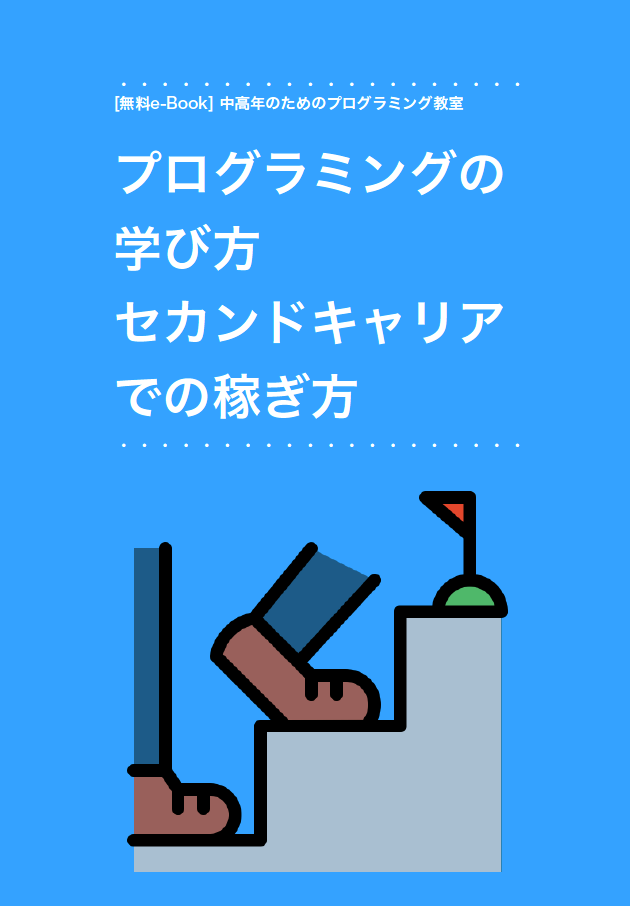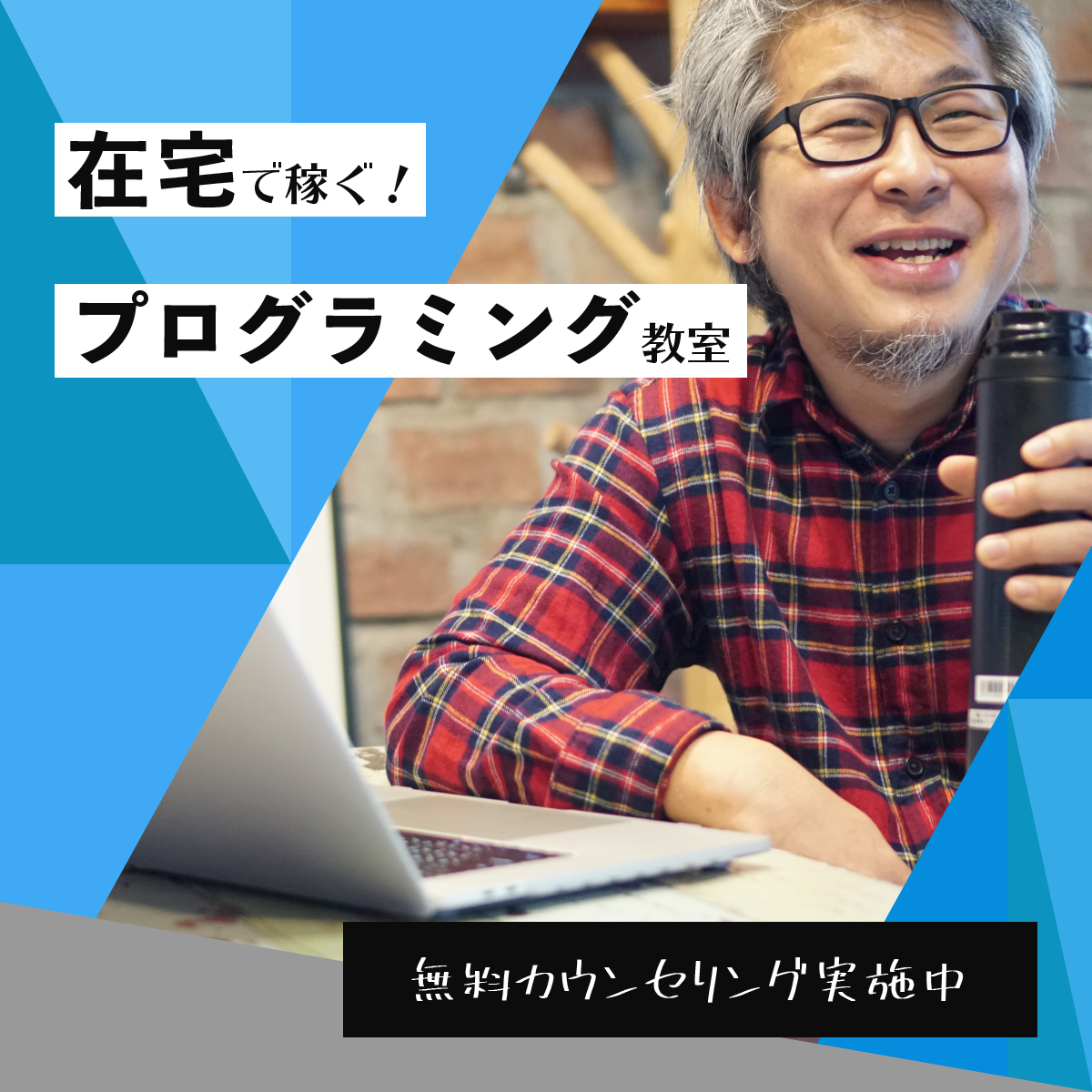70歳定年法時代を生き抜く① 70歳まで長く働けるメリットはあるが収入減がデメリット。早くからの学び直しと稼ぎ直しで対応すべき
更新日:2024.07.01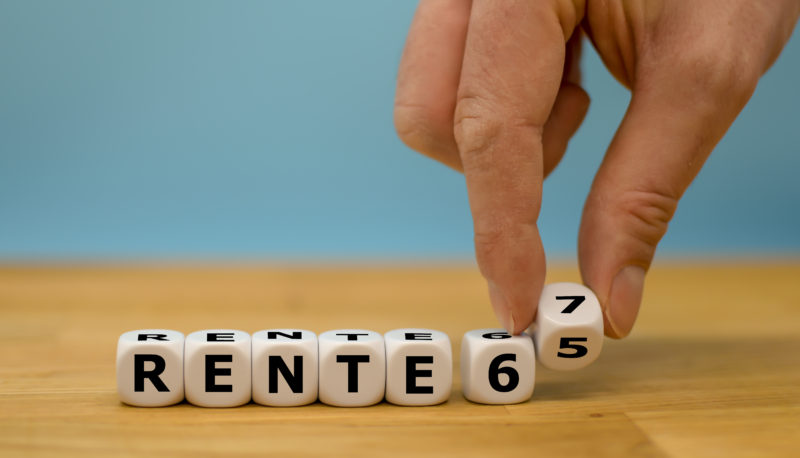
2021年4月に、70歳まで就業機会の確保が努力義務となる、改正高齢者雇用安定法、いわゆる「70歳定年法」が施行されました。
70歳まで会社にいれるのはありがたい、と思う方もいるでしょう。
しかし、実は70歳定年法が施行されたからといって、一律に「定年」自体が70歳に引き上げられるわけではなく、「就業機会の確保」が強制力のない「努力義務」として定められるだけですから、実態としてどうなるかを見定める必要があります。
そこで、今回は
70歳定年時代を生き抜く① 70歳定年法の制度内容やメリット、デメリットは?
70歳定年時代を生き抜く② 死ぬまでの収入を確保する方法
70歳定年時代を生き抜く③ 中高年・シニアの仕事の探し方(在宅勤務、地方案件有)
と三回に分けて制度の解説や予測される生活の変化、更にその具体的な対策までお伝えしていきます。
70歳定年法が施行されたことによる、メリットとデメリットの両方があります。
本記事では、70歳定年法の制度内容からその導入によるメリット・デメリット、70歳定年法を迎えるにあたっての人生設計の基本的な考え方まで解説します。
目次
結論:長く働けるメリットの一方で収入減がデメリット 。セカンドキャリア設計を元に学び直しと稼ぎ直しで対応すべき。
定年が70歳まで伸びる事は、「長く働ける」という単純なメリットはありますが、一方で「同じ仕事をしているのに現役の時よりも収入が減ってしまう」というデメリットもあります 。
働き慣れた会社で今までと同じ仕事を続ける選択よりも、今のうちにセカンドキャリア設計を行い、必要な学び直しや稼ぐポイントの見直しを検討して、定年の制度変更に振り回されないよう周到に準備しておきましょう。
70歳定年法とは
まず初めに、「70歳定年法」について ①概要② 背景③ 内容と変更点 の3つに分けて解説していきます。
1)概要
「70歳定年法」は、2021年4月に政府が会社に対して施行した「全従業員が70歳まで就労する機会を確保するように努力義務をしなければならない」という法律です。 あくまで「努力義務」ですので、「今すぐ定年を70歳としなければならない」というものではありません。
しかし、後述する「2)背景」により、近い将来「70歳まで定年が引き上げられ,同じ会社で働く選択肢を与えられる」可能性は十分にあるでしょう。
例えば家電量販店のノジマは、上場企業としては初めて、全従業員が80歳まで一年契約で働き続けることが出来る制度に変更しました。
参照:定年後、最長80歳まで雇用を延長(2020.7.28)
2025年4月からすべての企業に対して「65歳への定年の引き上げ」「定年廃止」「65歳までの継続雇用制度」のいずれかが義務づけられることになります。
これだけでは現状の「60歳で定年を迎えた後も、5年間同じ会社で働く選択肢を与えられる」という仕組みが5年間後ろ倒しになっただけのように思えます。しかし、70歳定年法では新たに、フリーランスを始めとした「同じ企業で働かない選択肢が用意される」という画期的な施策も盛り込まれています。
具体的には、他の企業への再雇用支援やフリーランスで働くための資金提供、起業支援、NPO活動への資金提供といった選択肢が増え、今までになかった働き方もできるようになります。 「新しい働き方」の促進は企業の立場から見ると「定年延長によって増える人件費を抑える」という見方もできます。
2)背景
厚生労働省の資料によると、70歳定年法が施行された背景は2つあります。
1つ目は、少子高齢化による、生産年齢人口(15歳から64歳)の減少です。 そもそも、日本の人口は年々減少傾向にあり、令和元年8月から令和2年8月の1年間だけでも41万人減少しています。 その中でも減少が著しいのが生産年齢にあたる15歳から64歳の間で、1年間で52万人減少しています。
一方で65歳以上は31万人増加していることから、65歳を定年とすると労働人口は一気に21万人減少してしまいます。 個人事業主などの働き方で65歳を過ぎても継続して働いている方はいますが、60歳を定年と定める会社も未だに多いのが現状です。
生産年齢人口のうちの労働人口が、21万人よりさらに減っていくことは容易に想像がつきます。 生産年齢人口の減少は会社の人手不足を深刻化させるだけでなく、日本経済にも影響を及ぼします。
2つ目は、社会保障を持続させることです。 2017年度に充てられた年金や医療、介護などによる社会保障費は116.9兆円で、前年度より1.3%増加しました。増加傾向は今後も続き、2040年には高齢者の人口が全体の4割前後となり、現在の社会保障制度のままだと社会保障給付費は約190兆円にのぼると言われています。
そして先ほども紹介したように、生産年齢人口は減り続けているため、このままでは今の社会保障制度を維持することは難しくなります。 これらの要因が、定年の引き上げを行う「70歳定年法」が施行される背景です。
3)内容と変更点
ここからは「70歳定年法」の詳しい内容と追加された変更点について解説します。
内容
まずは、以前に施行されていた「65歳定年法」についてご説明します。 企業は60歳を迎える従業員に対し、次のうちのいずれかの方法を取ることが求められます。
① 定年を65歳までに引き上げる② 65歳までの継続雇用制度(再雇用)を導入する ③ 定年制度を廃止する そして、「70歳定年法」では「65歳定年法」の項目を5年延長しただけでなく、新たに2項目が追加される内容となっています。
① 定年を70歳まで引き上げ
② 70歳までの継続雇用制度(再雇用)の導入
③ 定年廃止
④ 高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に社会貢献事業に参加する制度の導入
定年や再雇用の引き上げはもちろん、新しい働き方として「業務委託契約」や「社会貢献事業」が追加されました。 業務委託契約と社会貢献事業は必ずできるわけではなく、労働者の過半数を代表する労働組合もしくは労働者の過半数を代表する者の同意のもとで選択できるようになります。
では、追加された2項目について詳しく説明します。
変更点①:業務委託契約
1つ目が「業務委託契約」です。 業務委託契約とは、65歳以上でフリーランスや起業家になった従業員に対し、企業が業務を委託する形で継続的に働くことができる制度です。 例えば、定年後にあなたがプログラマーのフリーランスになったとすると、企業ホームページのリニューアルや社内ポータルの整備や変更を任されるといったことです。
もちろん、強制ではなく希望制です。 とはいえ、フリーランスが軌道に乗ってある程度の収益をあげるには、実績を作ることが必須なので、勤務先から仕事を与えてもらえる制度はありがたいのではないでしょうか。
変更点②:社会貢献事業
2つ目が「社会貢献事業」です。 社会貢献事業には、大きく分けて2種類あります。 最初に「事業主自ら実施する社会貢献制度」についてです。 企業には「企業の社会的責任」が伴うことから、地域貢献や生活安全、環境保全などの社会貢献制度を行っています。
イメージとしては、休日に行われる労働組合のイベントのようなもので、イベントの主催や地域貢献をするために働くといったものです。
次に「事業主が委託、出資(資金提供)などをする団体が行う社会貢献事業への参加」についてです。
イメージとしては各自治体が介護や虐待で悩む人の相談を受ける相談員で、勤務先によってどのような団体で働けるかは異なります。 NPO活動へのサポートが代表例です。
70歳定年法:個人のメリット
次に「70歳定年法」が施行されることにより受けられる「個人のメリット」を3つご紹介します。
メリット①:安定した収入の確保
まず一番目のメリットとして「安定した収入の確保」が挙げられます 。70歳になるまで働き続けられれば、その間継続的な収入を得る事ができます 。毎年のように年金受給年齢の引き下げが議論される不安定な中、老後の資金を心配する事なく生活できることはやはり大きなメリットと言えます。
また仕事を続けることで、社会とのつながりを保ち、生きがいを感じられることもメリットの一つです。
定年70歳の義務化が開始!70歳まで働くメリット・デメリットについてもご紹介
メリット②:セカンドキャリアの選択肢が増える
二番目のメリットとして挙げられるのは「セカンドキャリアの選択肢が増えること」です。70歳まで働くことで、自分自身の更なるスキルアップや新しい分野への挑戦が可能になります。また、今まで培った経験を基に社会貢献できる仕事に就いたり、長年の趣味を仕事にすることもできます。
また、企業側も高齢者に対する採用や再雇用に積極的になり、高齢者のスキルや経験を活かした仕事を提供する、という可能性も出てくるでしょう 。
メリット③:働く期間が長くなり、生きがいを感じられる
「働く」ということは、人生の中であなたが想像する以上に大切なことです。 定年を迎え退職した後に、無気力になったり精神的に不安定になったりする「燃え尽き症候群」になるという人もいます。
燃え尽き症候群は、働くことそのものや会社の中で の「役割」が突然なくなることで、精神的にしんどくなることです。 働く期間が長くなることで、燃え尽き症候群のリスクを減らすことができることはもちろんですが、それだけではありません。
「70歳定年法」によって新しい働き方の道を選んだ場合は、働き方そのものや必要なスキルを身につけることから、新鮮味や成長意欲から生きがいを感じられます。
70歳定年法:企業側のメリット
次に「70歳定年法」が施行されることにより受けられる「企業側のメリット」について2点ご紹介します。4−5年後、バブル世代が60歳を迎え、大量に退職することによる人材不足が懸念されているため、企業側の雇用継続は急務の課題と言えます。
メリット①:安定した戦力として期待される
ベテランとして活躍したあなたの能力は、企業にとって大きなメリットとなります。 現在、多くの企業で人材不足が深刻化しており、新たな人材を確保することが難しくなっています。
派遣社員や契約社員という「正社員でない雇い方」で人を採用することはできますが、大半の人が数年で会社を去るため、優秀な人材であっても企業の戦力としては不十分です。
同じ会社に長く務め、会社の仕組みや業務、立ち位置などがわかるあなたのような人材は「安定した戦力」として企業から重宝されます。
メリット②:若手に専門スキルや知識をじっくり引き継げる
従業員が会社で培った専門スキルや知識は、企業にとって「財産」とも言えます。 しかし、定年ギリギリまで最前線で働いている人の場合、目の前の仕事に集中しないと仕事が回らず、後輩に十分な引き継ぎができないまま退職するケースも多く見られます。
高いスキルを受け継ぐ人材が増えれば社内全体の業績も上がるため、若手に専門スキルや知識を引き継ぐことは、企業が将来生き残るうえで欠かせません。70歳まで継続して最前線で働く場合は難しいかもしれませんが「65歳からは一線を退いて若手の指導に従事する」という働き方を求められる機会が増えてくるかもしれません。
70歳定年法:個人のデメリット
ここからは「70歳定年法」が施行されることにより受ける「個人のデメリット」について3点ご紹介します。
デメリット①:高いスキルなのに低賃金という状況を助長する可能性がある。
70歳定年法が施行されることで、「賃金水準の低下」が懸念されます。 現在は65歳定年が努力義務となっていますが、実際は60歳で定年を迎えたのち、再雇用としている企業が8割以上となっています。
企業が定年延長ではなく再雇用を選ぶ理由は、「再雇用の方が給与を大幅にカットでき、人件費を減らせる」という思惑のためです。再雇用で 給料が安くなると、働くモチベーションが下がったり、現在の生活水準を維持するために転職・再就職をせざるを得なかったりします。
また、再雇用でも高いスキルや経験を持っている人は多いのに「再雇用」という雇用形態のために、貢献度に見合わない圧倒的に低い報酬で働く事が多いのもまた事実です。
もし60歳定年を維持したまま再雇用し、70歳まで再雇用するとすると、高いスキルや経験を持っている人材が10年もの間、大幅に削減された給与で働き続ける、というミスマッチが生じる可能性があります (最も、真に高いスキルや経験のある人材は好条件で他の仕事を見つけられる時代になるとは思いますが)
そして、再雇用による賃金低下であなたのモチベーションが低下するだけでなく、あなたと同じ職場の後輩のやる気にも影響を及ぼす可能性も高まるでしょう。
デメリット② 年金が減る可能性も
65歳以降も働き続ける事で、年金の受け取りがカットされるかもしれないというデメリットが生じる可能性があります。また、定年後「企業に雇用される状態」で働き続ける場合、70歳までは保険料の支払い義務が発生する場合があります。(厚生年金の加入条件を満たす雇用形態の場合に限る)
参照元:定年後も働くと年金カットって本当?70歳まで現役でいるメリット・デメリット | ジョブジョブメディア (jobjobmedia.com)
デメリット③ 新しい環境や仕事を求められる
定年後再雇用になった場合、必ずしも同じ部署・同じ業務・同じ役職で採用されるわけではありません。新しい部署や仕事に配属される場合もあり、今まで経験したことのない業務や作業を強いられるケースもあります。
また、現在国がDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進しているため、今後急速に業務のデジタル化が進むことが考えられます。
デジタル化やDX化を求められ、変化についていけるのかと不安に感じながら働く必要があることもデメリットの一つと言えます。
70歳定年法:企業側のデメリット
次に「70歳定年法」が施行されることにより受ける「企業側のデメリット」について3点ご紹介します。
デメリット① : 人件費の上昇
70歳まで雇用を続ける場合の企業側のデメリットとして「人件費の上昇」が挙げられます。定年延長により、高齢者の雇用が増えることで、企業は高齢者に対する賃金や福利厚生などの負担が増える可能性があります。また高齢者の雇用に人件費を費やすことにより、若年層の雇用機会が減少する可能性も出てきます。
デメリット②:モチベーションの低下
70歳定年法による働くモチベーションの低下は、現在50代後半~60代前半の方に見られることが多いです。 50代後半~60代前半の中には、もうすぐ定年でセカンドライフを楽しみにしながら働くモチベーションを高めている人もいるでしょう。 しかし、定年が遠のき、終わりが見えなくなることから、仕事に対するやる気が落ちてしまいます。
マラソンに例えると、40km地点まで到達したのに、40km地点で「ゴールが5km延長して47.195kmになりました」といわれるのと同じ状況です。 働くことに対するモチベーションの低下から、燃え尽き症候群や不安におちいり、50代で失業する人や精神疾患を患う人が増えるというリスクもあります。
デメリット③:若い世代の出世の難易度が更に上昇
「出世の難易度が上がる」ことも、70歳定年法によるデメリットの一つです。 特に年功序列制度が強く残っている会社ほど、出世をすることが難しくなります。定年年齢が上がると、当然役職になる最低年齢も上がります。
例えば、課長は30歳から40歳に引き上げられ、部長も40歳から50歳に引き上げされるといったようなものです。さらに、会社が簡単に人を解雇できないことも相まって、役職ポストに空きができにくくなるため、同じポストに居続ける人も増えてきます。
「 頑張っても出世できない」という状況に若い世代が嫌気を感じ、仕事に対するモチベーションも低くなってしまうでしょう。
70歳定年法による人生設計の変化
「70歳定年法」が施行された後も、活躍し続ける人材になるためには、人生設計や考え方をこれまでと変えていくことが大切です。ここからは「 70歳定年法による人生設計の変化」についてご紹介していきます。
1)働き続ける
70歳定年法が施行されると、当然働く期間が増えます。今60代の方は70歳までは働き続けることになる可能性が高いですし、50代の方は今後さらに70歳を越えて80歳まで何らかの形で働き続けることになるかもしれません。
これから長い期間働き続けるためにもスキルを磨いたり、安全面や体調管理に気を配ったりすることが、今まで以上に求められてきます。当然、年金に頼らない収入の設計も必要になってくるでしょう。
2)働き方の変化を楽しむ
70歳定年法が施行されると、今まで以上に多様な働き方ができるようになります。 例えばセカンドキャリアとして起業したり、フリーランスとして生活したりするなどの生き方の選択肢が広がります。
とはいえ、これまで親や上司、同僚の背中を見て「1つの会社で仕事を全うして、年金生活で悠々と過ごす」といった理想を抱いている人にとっては、ネガティブなギャップかもしれません。
今後、「働き方の変化を楽しむ」というマインドセットを獲得し、新しい働き方のためのスキルを身につける「柔軟性」が、70歳定年法が施行された後の社会を生きる上での鍵になるのではないでしょうか。
70歳定年法のメリットを最大化するために
70歳定年法のメリット(収入が安定する、選択肢が増える)を最大化し、デメリット(高いスキルなのに低賃金、年金が減る、モチベーションの低下)を最小化するためには、定年前の50代のうちにライフプラン、マネープランを元にセカンドキャリアプラン戦略を設計することが必要です。
その過程で、自分の今までの経験とスキルを棚卸しを行い、目指すセカンドキャリアプランとのギャップを埋めるための活動が リスキリング「学び直し」と 自ら仕事を探索したり案件を獲得しマネタイズまで持っていく「稼ぎ直し」スキルとなります。
セカンドキャリアプラン戦略と「学び直し」「稼ぎ直し」の概要を以下のスライドにしました。
セカンドキャリアプラン戦略と「学び直し」「稼ぎ直し」の概要
TechGardenSchoolでは学び直しのためのプログラミングクラスだけでなく、「セカンドキャリア設計クラス」「初めてのクラウドソーシングクラス」「中高年のためのジョブハンティングクラス」といった、セカンドキャリア戦略設計と稼ぎ直しのクラスもご用意しております。 ご興味のある方は、無料カウンセリングへのお申し込みをご検討ください。
まとめ
今回は「70歳定年法時代を生き抜く①」と題して、70歳定年法が施行される事で受けるメリットとデメリット 、変えていきたい考え方や人生設計、メリットを最大化するための方法についてご紹介してきました。
定年が70歳まで伸びて「安定した収入を得られる」「セカンドキャリアの選択肢が広がる」というメリットがありますが、一方で「現役時より収入が減って仕事へのモチベーションが下がる」「もらえる年金額が減る可能性がある」というデメリットもあります 。
定年前の50代のうちにライフプラン・マネープランを見直し、セカンドキャリア設計を行いましょう。必要なリスキリング(学び直し)と 自ら仕事を探し案件を獲得できる「稼ぎ直しスキル」を身につけて周到に準備をしておけば、先を見通しずらい雇用制度の変更に振り回される心配もなくなります。
次の記事(70歳定年時代を生き抜く② 死ぬまでの収入を確保する方法)では、もう少し踏み込んで実際に70歳定年法が施行されると収入がどのように変化し、どのような準備が必要になってくるのか、お伝えしていきます。
参照元:
「70歳定年」で30~40代の昇進が絶望的な理由 年功序列の「日本株式会社」は変われないのか (東洋経済オンライン 2020/10/23 )
定年後再雇用の実情、給与激減・人間関係微妙でも残るべきか (Diamondオンライン 2018/5/7)
セカンドキャリア向けの無料コンテンツもあります!

2021年4月に、70歳まで就業機会の確保が努力義務となる、改正高齢者雇用安定法、いわゆる「70歳…

近年、自宅で働ける在宅ワークの働き方が浸透してきたことから、外出頻度が落ちるシ…
20年以上に渡り金融機関に勤務している「生粋の金融人」です。FP仲間の情報や勉強会・お金にまつわるニュース等をわかりやすく簡単な言葉で発信しています。 FP技能士2級・AFP・日商簿記2級