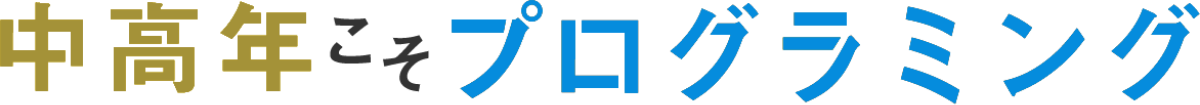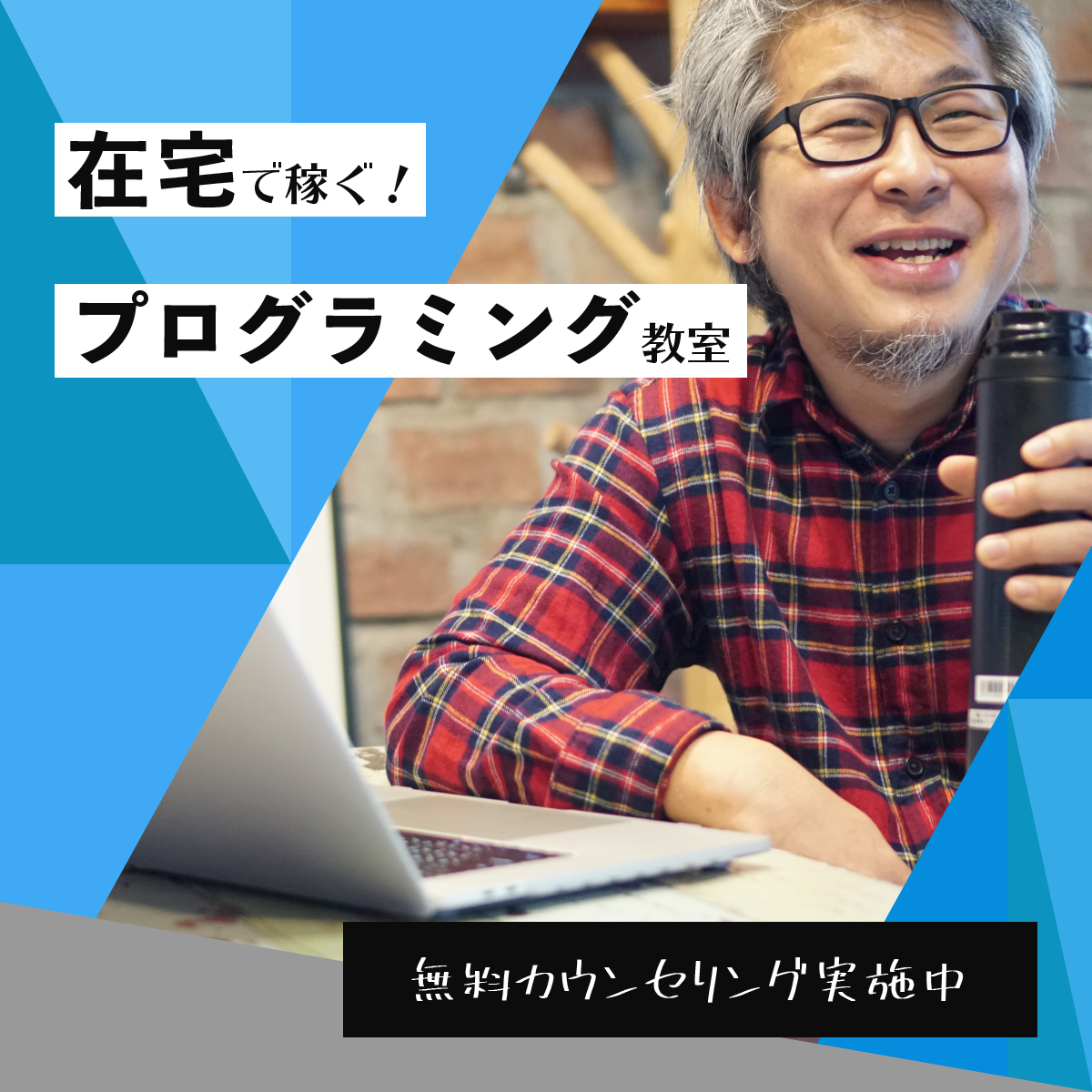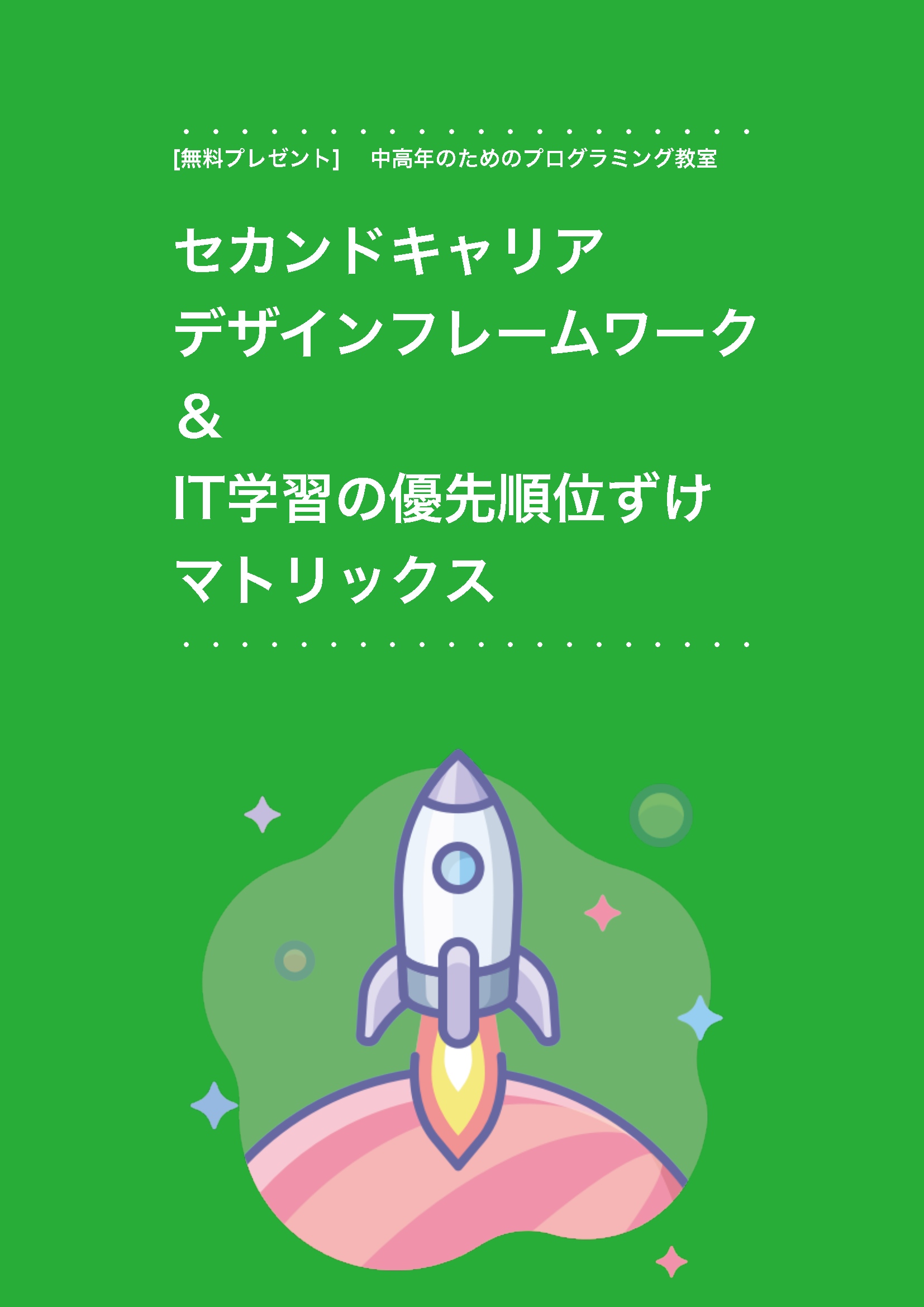50代会社員が直面する「役職定年」をつらいものにしないための準備とは?
更新日:2024.05.26
それまで積み上げてきた役職を、ある年齢に達したと同時に解かれる「役職定年」は、大きなキャリアの転換点です。「年収が下がる」「モチベーションが保てない」など、悪いことばかりに感じられる役職定年をみじめなものにしないためには、どのような準備が必要なのでしょうか。
この記事では、役職定年をポジティブに迎えるために、今からできる準備について考えていきたいと思います。
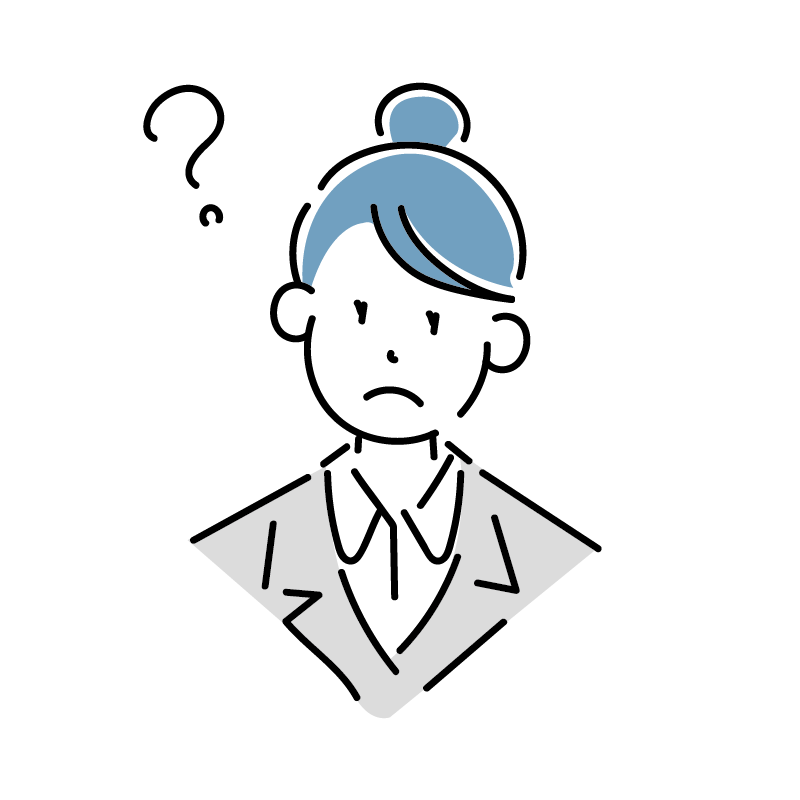
50代会社員です。我が社にも役職定年の制度があり、年収も半減すると聞いて恐々としています。役職定年になるつらさとは実際にはどんなものなのか今から知っておきたいです。 また、何か今から打てる手立てはないでしょうか?
役職定年を「つらい」と感じる要因として、1)年収の大幅ダウン 2)地位と権限がなくなる 3)モチベーションの低下などが挙げられます。役職定年をプラスに変えていくためには、役職定年をキャリアシフトの準備期間と前向きに捉え、まずはしっかりとライフプランやマネープランを計画することが大切です。そのうえで、これまでの経験や今後の希望を踏まえ、あなた自身のセカンドキャリアプランを設計していきましょう。そしてセカンドキャリアプランから逆算して、新しいスキルを習得する「学び直し」や今の会社に依存せず自分の力で仕事を獲得して収入を得る「稼ぎ直し」スキルを磨くことも重要です。
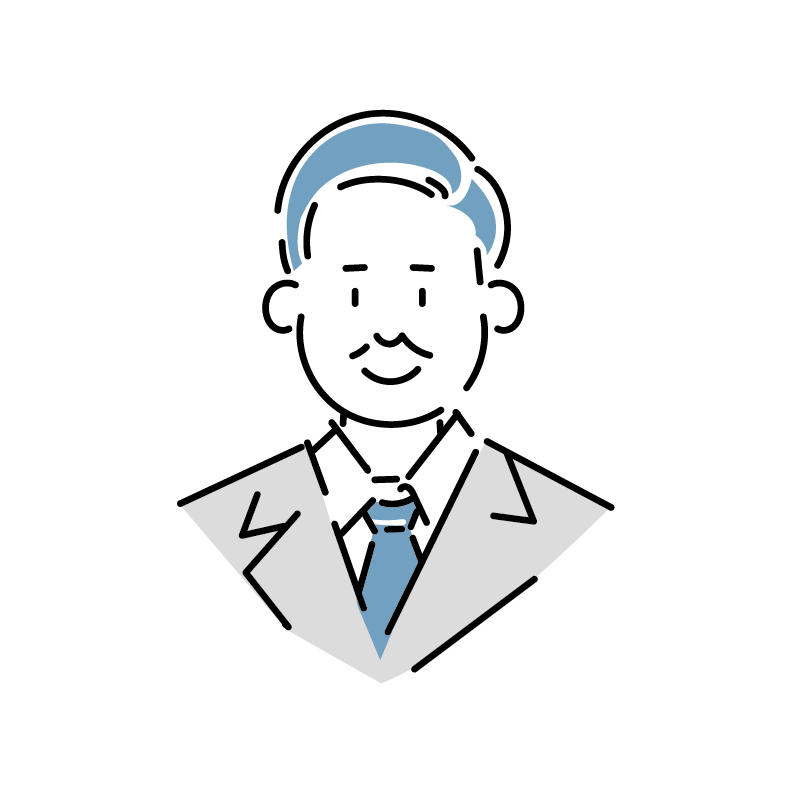
目次
結論:役職定年をつらいものにしないために、キャリアプラン戦略を立て年収減に備えるべき
役職定年は、年収減少やモチベーションの低下、居心地の悪さなどの「つらさ」「みじめさ」に着目されがちですが、一方で時間的・精神面に余裕が生まれるなどのメリットもあります。
役職定年をつらいものにしないためには、役職定年をキャリアシフトの準備期間と捉える心構えと、ライフプランやマネープラン、キャリアプランをしっかり計画することが重要です。
加えて、キャリアプランから逆算した「学び直し」と、自ら仕事を獲得しマネタイズまで持っていく「稼ぎ直し」も必須スキルとなります。
役職定年とは
はじめに、役職定年の内容や企業側の狙い、海外での考え方について解説します。
役職定年の内容
役職定年とは、企業の各役職(ポスト)に定年を設定し、その年齢に達したら役職から外れる制度です。たとえば、55歳などの規定の年齢になると部長や課長といった管理職から外れ、専門職に移行することになります。
経団連から発表された資料によると、役職定年制を導入している企業は約5割に達します。役職定年の年齢はそのうち55 歳が31.5%、57 歳が25.9%と、50代が導入する企業の約8割に上ります。また、役職定年を導入していない企業でも、定年到達後の再雇用に伴って、役割や責任の範囲が縮小する場合があるといいます。*1
*1 ホワイトカラー高齢社員の活躍をめぐる現状・課題と取組み.経団連.2016年5月17日
企業側の狙い
企業が役職定年を設けている大きな狙いとして、企業・組織の新陳代謝の促進が挙げられます。企業が持続的な成長を実現するうえでは、現在の組織体系に固執せず、常に若手や中堅層を育成していくことが重要です。
そして若手や中堅層を育成するためには、なるべく早い段階から役職についてもらい、業務上の権限や責任を与えていくことが大切になります。また、役職定年が定着しつつある背景には、総人件費のコントロールや高齢化による定年延長も挙げられます。
以前は55歳定年だったものが、2025年からは定年制を採用しているすべての企業において65歳定年制が義務化されます。それによって社員のボリュームゾーンが高齢化するため、企業は役職定年を活用しながら組織運営の舵取りを行っていく必要があるのです。
役職定年、海外での考え方
日本企業ではよく見受けられる役職定年ですが、海外ではそもそも年功序列の考え方がありません。キャリアは自分で守るものであり、社員は年齢に関係なく実力やスキルに応じたポジションが与えられます。そしてこのような考え方は、日本でも徐々に導入されています。
高齢化に伴い中高年の社員の割合が高くなる中で、「役職定年」のように社員のやる気を低下させるようなシステムではなく、年齢に関係なく職務を果たせば評価される「ジョブ型雇用」を導入する企業も増えているのです。活躍が認められるような雇用システムであれば、シニアも働きがいをもつことができ、企業への貢献が期待できるという考えです。
役職定年の「つらさ」「みじめさ」とは?
役職定年は、企業側にとっては組織の新陳代謝促進につながる制度ですが、対象となる社員にとっては以下の理由から「つらさ」や「みじめさ」を感じるケースも多いといえます。
年収が下がる
役職を解かれると役職に伴う手当はなくなり、年収も当然低くなります。あるアンケートでは、役職定年で9割以上の人が年収減となっています。年収水準としては50~75%が最も高い割合を示してはいるものの、約4割の人の年収額が50%未満になるという結果が出ています。*2
なお、退職金については減少はするものの、年収ダウンに比べれば限定的であるため、そこまで深く考える必要はないでしょう。役職定年後の年収や退職金の詳細については、以下の関連記事も合わせてご確認ください。
関連記事:
「【50代会社員マネープラン】役職定年になると退職金も減るのか?年収はどうなるの?」
*2 50代・60代の働き方に関する意識と実態.明治安田総合研究所.2018年
居心地の悪さ
役職定年の際に所属移動がなく同じ部署で働く場合、
・元部下が上司になり、自分自身仕事がやりにくい
・元上司だった自分が同じ職場にいると、元部下がやりにくそう
という、両方向の居心地の悪さを経験する人も少なくないようです。一方、所属移動があった場合でも、それまでの経験やスキルをいかせないというフラストレーションを感じる可能性があります。
慣れない仕事になることも
役職定年によって所属移動を行った場合、今までの部署とは全く異なる仕事内容になるケースもあります。たとえば、これまで経理一筋で仕事をしてきた人が、役職定年によって営業事務などに回るような可能性もあるでしょう。慣れない仕事になることで、仕事から受けるストレスや不安が強くなるおそれもあります。
モチベーションの低下
さきほどのアンケート*2によると、年収が下がった人はもちろん、役職定年の際に年収が変わらなかった人の4人に1人が「モチベーションが下がった」と答えています。役職はその組織で任されている責任を象徴するものであることを考えると、「役職がなくなった」という事実そのものが、モチベーションを低下させる原因にもなってしまうようです。
役職定年のメリット
「つらさ」「みじめさ」のある役職定年ですが、一方で以下のようなメリットもあります。
仕事のプレッシャーがなくなる
メリットのひとつに、役職から外れることで仕事のプレッシャーがなくなる点が挙げられます。たとえば、これまで課長として働いていた場合、部署の予算管理や業績管理、部下のモチベーション管理といったさまざまな責任を感じていたでしょう。役職定年によって管理職から離れれば、そのような仕事上のプレッシャーからも解放されることになります。
時間的余裕ができる
役職定年によって仕事上の責務が少なくなることで、時間的余裕もできます。空いた時間で、新しいことに取り組んだり、家族との時間・趣味の時間を楽しんだりすることが可能です。つまり、役職定年はプライベートを充実させるきっかけにもなるということです。
精神的余裕ができる
役職定年後は、精神的余裕ができる点もメリットです。組織責任者としての管理業務や責任がなくなることで、心に余裕を持って仕事に取り組めるようになります。それにより、日常の仕事のなかで新しい発見をしたり、クリエイティブなアイデアを創造したりできる可能性もあるでしょう。
役職定年を上手く活かせる人・活かせない人
ここでは、役職定年を上手く活かせる人・活かせない人の主な特徴について解説します。
役職定年を上手く活かせる人
役職定年を上手く活かせる人の大きな特徴は、自分自身のセカンドキャリアプランをしっかりと持っている人です。自分自身の希望に基づいてセカンドキャリアプランを明確にしているため、役職や年齢に関係なく、計画的に準備・学習を続けていくことができます。
また、セカンドキャリアプランを描くうえでは、現在の会社だけに固執せず、別の会社や独立などのさまざまな選択肢も柔軟に視野にいれています。加えて、家族や趣味の時間も積極的に計画しているため、役職定年後の人生を充実させることができるでしょう。
役職定年を上手く活かせない人
一方で、役職定年を上手く活かせない人は、セカンドキャリアに対する自分の軸がはっきりしていない人です。自分の軸がはっきりしていないため、「役職ありき」の仕事になってしまい、役職定年によって「つらさ」や「みじめさ」を強く感じてしまう傾向にあります。
役職定年をマイナスの出来事にしないためには、年齢や役職に依存せずにあなた自身が希望するライフプランやキャリアプランを描いていくことが重要です。
役職定年を上手く活かした人の事例
ここで参考として、役職定年を上手く活かした人の事例をご紹介します。ソニー株式会社で勤務し、56歳で役職定年を迎えた芳賀氏は、役職定年後にチーム育成のコンサルタントとして起業・独立しました。
役職定年による年収ダウンよりも「60代になったときに人の役に立てているか」に目を向け、大企業の看板を捨てて新しいチャレンジに踏み出した事例です。芳賀氏は、なるべく初期費用を抑えながらこれまでの自分の経験を活かす道としてコンサルタントを選択し、企業に対して研修プログラムなどを提供しています。役職定年をピンチではなくチャンスに変えた良い事例であるといえるでしょう。
事例の詳細については、以下の参考記事も合わせてご確認ください。
参考記事:
プロ50+ 2019.12.11「【起業事例】役職定年を機に退職、チーム育成のコンサルタントとして独立」
役職定年をポジティブに迎えるための心構えと準備
ここでは、役職定年をポジティブに迎えるための心構えと準備について解説します。
心構え : 役職定年はキャリアシフトの準備期間と捉える
健康寿命が延長化するにつれ、人生の中で働く期間も長くなっています。現代社会においてシニアはキャリアを引退する時期ではなく、新しい方法でキャリアを始める、いわば「セカンドキャリアを始める時期」であると言えるでしょう。
キャリアにおける大きな転機となるのは、ほとんどの人にやってくる「定年」です。定年後のキャリアには、再雇用・再就職・フリーランス・起業などの選択肢が考えられますが、どれを選択するにせよ、今までのキャリアを一旦棚卸しし、新しい価値観でキャリアを再出発させる必要があります。
役職定年は、定年前に与えられた「キャリアシフトへの準備期間」とも捉えることができます。役職を離れることで仕事の負担や責任が軽くなり、気持ち的にも時間的にも定年後の働き方を考える余裕が与えられると考えることもできます。
準備
年収減少に備える
役職定年のつらさとして最初に挙げられる年収減少に対する備えを早いうちから始めることは、最も大切な準備だといえます。具体的には、月々の支出の正確な把握や年金を含めた収入の手立ての計画、資産運用、副業などです。
ライフプランやマネープランを計画し、役職定年後の年収だけでは不安な場合は、減収をカバーする具体的な対策をとることも必要となります。マネープランの詳細については、以下の関連記事も合わせてご確認ください。
関連記事:
「【50代会社員マネープラン】役職定年になると退職金も減るのか?年収はどうなるの?」
セカンドキャリアプランを設計する
役職定年をつらく、みじめなものにしないためには、役職定年になる前にライフプラン、マネープランを基にセカンドキャリアプラン戦略を設計することも必要です。セカンドキャリアプラン戦略を設計する際は、自らの「キャリアアンカー」(仕事に見いだす価値)を考えることが大切です。
キャリアアンカーは、自由や挑戦、他者貢献など、人それぞれによって異なるため、先入観を捨ててあなた自身のキャリアアンカーを見つけましょう。そうは言っても、キャリアプランを立てた経験のない方も多いのではないでしょうか。
具体的なキャリアプランの立て方については、以下の関連記事も合わせてご確認ください。
関連記事:
「【50代会社員のセカンドキャリア】希望のキャリアを実現するための準備や支援とは?」
関連記事:
「50代からのキャリアプランはスキルの掛け合わせで考える。シニア年代で活躍し続けるために大切なこと。」
セカンドキャリアプランから逆算でリスキリングをしよう!
セカンドキャリアプランを設計したら、自分の今までの経験とスキルを棚卸しを行い、目指すセカンドキャリアプランとのギャップを埋めていきましょう。そのための活動がリスキリング「学び直し」と、自ら仕事を探索したり案件を獲得しマネタイズまで持っていく「稼ぎ直し」スキルとなります。
フリーランスや起業、転職など選択肢はさまざまですが、いずれの場合でも「学び直し」と「稼ぎ直し」スキルは必須です。役職がなくなったことで生まれた時間的・精神的余裕を、資格取得やスキル取得のための学びに振り向けることを考えてみましょう。
セカンドキャリアプラン戦略と「学び直し」「稼ぎ直し」の概要を以下のスライドにしました。
セカンドキャリアプラン戦略と「学び直し」「稼ぎ直し」の概要
TechGardenSchoolでは学び直しのためのプログラミングクラスだけでなく、「セカンドキャリア設計クラス」「初めてのクラウドソーシングクラス」「中高年のためのジョブハンティングクラス」といった、セカンドキャリア戦略設計と稼ぎ直しのクラスもご用意しております。
ご興味のある方は、無料カウンセリングへのお申し込みをご検討ください。
まとめ
役職定年は、年収減少やモチベーションの低下といったマイナス面が先に立って「つらさ」が強調されがちです。しかし漠然と不安を抱えたまま、ただその日を待っていることは得策ではありません。役職定年をつらいものにしないためには、年収減に備えたライフプランやマネープランを立てつつ、キャリアプラン戦略もしっかりと設計することが大切です。
役職定年を前向きに捉えて、セカンドキャリアに向けた一歩を踏み出していただきたいと思います。
50代会社員に特化したセカンドキャリア支援ならTechGardenSchoolがオススメ!

50代を迎えた会社員は、これから50代後半にかけて役職定年を迎えます。役職定年とは、一定の年齢、5…
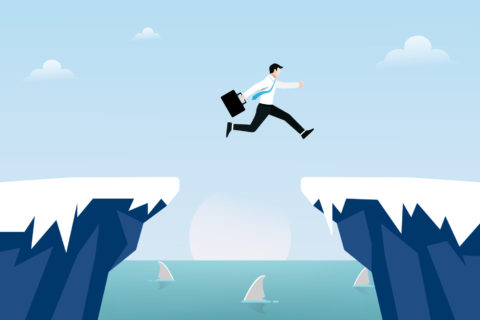
セカンドキャリアとは「第2の人生におけるキャリア(職業)」を意味する言葉です。もとはスポーツ選手が…

大手SIerおよび大手メーカーの情報システム部門で実務経験を積み、現在はITライターとして独立。DX・IT・Webマーケティング分野を中心に多数の記事やコラムを執筆。保有資格:ITストラテジスト、プロジェクトマネージャー、応用情報技術者など。